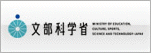沿革・目的・組織体制
沿革
歴史的には、10年の時限をもつ学内共同研究教育施設として発足した極低温エネルギー実験センター(1981〜1990年度)、引き続き発足した極低温システム研究センター(1991〜2000年度)、さらに極低温物性研究センター(2001年4月〜2010年10月)に受け継がれ、日本学術会議の研究拠点整備計画にも研究拠点として明記されるなど、東工大における低温研究を推進してきました。
2010年11月に共通施設として改組され、2016年4月には極低温研究支援センターの名称となりました。2018年10月には規則改正により、大岡山地区部門・すずかけ地区部門が置かれ、液体ヘリウムの安定的供給を中心に全学的に低温研究の支援を行っています。

目的
極低温研究支援センターは、寒剤(液体ヘリウム、液体窒素)供給、極低温に関する教育・研究支援及び共同研究の場の提供を目的としています。
上記目的のために、ヘリウムの回収と液化、低温技術や安全に関する講習会の開催、低温研究に関する研究会の開催、その他の啓蒙活動などを行っています。
寒剤供給に関しては、「寒剤供給・液化機」、講習会に関しては「低温技術講習会」、研究に関しては「研究紹介」「セミナー・研究会」、啓蒙活動については「公開講座・広報活動」のページもごらんください。

組織体制
メンバー
| センター長・大岡山セクション 教授(兼) | 藤澤 利正(理学院 物理学系) Email: fujisawa[at]phys.sci.isct.ac.jp |
ホームページ | 大岡山セクション 教授(兼) | 平原 徹(理学院 物理学系) Email: hirahara[at]phys.sci.isct.ac.jp |
ホームページ |
| 大岡山セクション 技術専門員 | 藤澤 真士(液化室: コアファシリティセンター 極低温研究支援部門) Email: fujisawa.m.b7e3[at]m.isct.ac.jp |
|
| 大岡山セクション 技術専門員 | 金本 真知(液化室:コアファシリティセンター 極低温研究支援部門) | |
| 大岡山セクション 一般技術職員 | 鈴木 裕子(液化室:コアファシリティセンター 極低温研究支援部門) | |
| すずかけ台セクション 教授(兼) | 川路 均 (総合研究院 フロンティア材料研究所) | ホームページ |
| すずかけ台セクション 教授(兼) | 東 正樹 (総合研究院 フロンティア材料研究所) | ホームページ |
| すずかけ台セクション 技術専門員 | 出川 悦啓(液化室:コアファシリティセンター 極低温研究支援部門) | 連絡先(学内のみアクセス可) |
センター運営委員会
センター長を委員長とし、学内の各部局から選出された教員(学長指名を含む)で組織されます。センターの運営全般(研究・液化業務、予算・決算承認等)やセンターの人事等に関する決定機関です。
センター専門委員会
センター職員および利用者の代表から組織された委員会。大岡山地区とすずかけ台地区それぞれに置かれます。主査は利用者かつ運営委員の中から選ばれます。センターの日常的な運営(研究・液化業務、予算案作成、共通実験スペースの配分審査、広報活動等)から将来計画におよぶまでの議論を行い、センターの運営に関する 助言を行います。